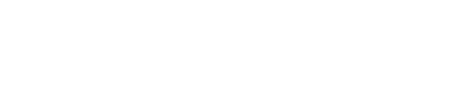辺見じゅん『収容所から来た遺書』(文春文庫)辺見じゅん『収容所から来た遺書』(文春文庫)
辺見じゅん 『収容所から来た遺書』(文春文庫)
・・・・・(前略)・・・・・
『収容所から来た遺書』で思い出すのは、講談社ノンフィクション賞の贈賞式で
す。作家の澤地久枝さんが選考経過を述べた際に、ともに選考委員を務めていた
立花隆さんがこの作品を絶賛したことに触れ、「世の巨悪を追及する際には容赦
ない鬼のような立花さんが、この作品を読んで涙が止まらなかったとおっしゃっ
た。あの立花さんでも泣くことがあるのか、と初めて分かった作品です」という
ようなスピーチをして会場を沸かせました。その時の立花さんの選評を読んでみ
ました。
〈辺見じゅん『収容所から来た遺書』は、脱帽に値する作品である。読みながら
思わず落涙した。これだけ人を感動させる作品はそうあるものではない。ノンフ
ィクションの良し悪しは半分は題材で決まり、半分は作者の力量で決まる。
この作品は、題材、作者の力量ともに申し分ない〉
今回、改めてこの本を読み返しましたが、感動はいささかも変わりませんでし
た。山本幡男(はたお)という本書の主人公の遺族が暮らす家を、終戦から12年
を経て、山本と同じソ連の強制収容所(ラーゲリ)にいたという男が訪れ、一家
の主に託された遺書を届けます。それから一通、また一通と郵送で、あるいは直
接持参する形で、全部で4通りの遺書――「山本幡男の遺家族のもの達よ!」の
呼びかけに始まる「本文」、「お母さま!」「妻よ!」「子供等へ」――が届き
ます。それらはすべて山本が最後の命の炎を燃やして綴った遺書でした。文字を
書き残すことはスパイ行為と見なされ、収容所を出発する前には厳重な私物検査
が行われ、字の書かれたものは、紙切れ一枚に至るまですべて没収するという監
視体制が敷かれていました。何としても山本の家族のもとにこれを届けなければ、
と考えた「心ある人々」は、それぞれ分担を決めて遺書を懸命に暗記し、写しは
衣服の中に縫い付けるなどして、必死で日本に持ち帰ったのでした。おそらくこ
うした例は「空前絶後のこと」だったと思います。
遺書は今回読み直しても涙がこみ上げました。寝返りも打てないほどの重病人
が、わずか一日の間にノートに15頁もの遺書を、まさに死力を振り絞って書きま
した。読んだ仲間たちは「これは山本個人の遺書ではない、ラーゲリで空しく死
んだ人びと全員が祖国の日本人すべてに宛てた遺書なのだ」と思い、「帰国の日
を待ちわびて死んでいった多くの仲間たちの無念の声を聞いている」ような気が
して、「なんとしてでもこの遺書を山本さんの家族に届けようという気持になっ
た」といいます。事実、山本が死んでから彼らが故国の土を踏むまでに、さらに
2年4ヵ月の試練が待ち受けていました。その間、「遺書を託された人びとにと
って、山本の家族に記憶して届けるということが、生きつづける支えともなった」
のでした。
こうした友情が育まれたのは、出口の見えない抑留生活にあって「山本の精神
の強靭さと凄さ」が皆に生きる力を与えたからでした。一見年寄りじみているの
に、目は意外に若々しく、誰にも分け隔てすることなく、周囲はしばしば笑い声
に包まれたという楽天的な人柄。極寒と飢餓と重労働に苦しめられ、精神的にも
過酷きわまりない収容所生活であればこそ、彼は繰り返し熱をこめて語ります。
「生きてれば、かならず帰れる日がありますよ」、「ぼくたちはみんなで帰国す
るのです。その日まで美しい日本語を忘れぬようにしたい」と。
そしてセメント袋を切った茶色い紙で綴られた文芸冊子をひそかに回覧するか
と思えば、「アムール句会」という俳句の集まりを呼びかけます。短冊はまたセ
メント袋を切って使い、馬の尻尾やマニラロープをほぐして毛筆を作り、「墨汁
の代用品は煤煙を水に溶かしてこしらえた」といいます。監視の目を盗むように
して集まり、終れば俳句を書きつけた紙は、土に埋めたり、“ハーモニカ便所”
の中に細かく千切って捨てました。
〈句会の集まりは、ラーゲリ内のとげとげしい雰囲気がウソのような別世界だっ
た。句会のときだけはみな日頃の作業の辛さも忘れる。むしろ作業中にも次の句
会に投ずる句などを考えていると、単調で辛い労働も違ったものに感じられてく
る。メンバーは、しだいに句会の楽しさにのめり込んでいった〉
こうして“希望”が生まれます。打ちのめされるような事件が起ころうとも、
そんなことにめげる様子もなく、「かえって逆境のときのほうが意気軒昂」だっ
たという山本は、病を得てもなお句会を欠かすことはありませんでした。やがて
アムール句会は200回目を迎えます。その時にはすでに出席が叶わなくなってい
た山本ですが、その報告を聞くと、「日本に帰ったら、ぼくたちのシベリア句集
を作ろう。……自分の句は記憶しておくようにみんなにいってくれよ」と語り、
次の歌を示します。
韃靼の野には咲かざる言の葉の花咲かせけりアムール句会
空前のシベリア句集を編むべきは春の大和に編むべかりけり
おそらく辺見さんが聞き届けたのは、この「言の葉」の力に寄せる信頼と、そ
れを糧に生と死の極限状況を生き抜こうとした山本の、そして無告の人びとの物
語だったような気がします。深く死者を悼むこと。近代の“防人”の運命に思い
を寄せ、彼らの挽歌を奏でることは万葉集に親しんだ辺見さんにとって、ごく自
然な流れだったと思われます。
・・・・・(後略)・・・・・